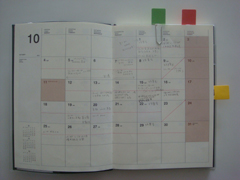こんにちは、IREC(国際リサイクル教育センター)センター長の鶫です。
新聞、マスコミはほとんど報じていませんが、12月1日からメキシコ・カンクンでCOP16が開かれています。10月に名古屋で開かれたのがCOP10ですが、COPとはConference of the Parties(締約国会議)の頭文字です。元の条約が共に1992年リオデジャネイロのサミットで締結された気候変動枠組み条約と生物多様性条約で、その第10回と16回会議ということです。
昨年コペンハーゲンで開かれたCOP15のテーマは2013年以降のポスト京都議定書を決める重要な会議でした。しかし、日本、EUなどと中国・発展途上国との対立が解けず、先送りとなりました。
今回テーマは京都議定書の延長論で、日本対EU・途上国とこれまでとは異なった図式です。そこで経産省と環境省の審議官がそろって「京都議定書延長はいかなる場合も認めない。」と共同戦線を張りました。これに対しEU、途上国+NGOは「会議を壊すものと」痛烈に批判しています。
日本の言い分は、中国、米国が入らない現在の枠組みは世界の排出量の27%しか拘束されず、不公正だというものです。確かに日本の主張は正しいのですが、この論理を通そうとすると京都議定書の生みの親が自ら首を絞めることになりかねません。EU、途上国の主張も13年以降の空白を回避するための備縫策に過ぎないのですが、多勢にはかないません。
日本の環境外交は1992年のリオから97年の京都、そして2000年に入って一貫性がなく失策続きです。その原因は、20数兆円払って海外から石油を輸入する化石燃料依存から脱却し、自前のエネルギーで賄う低炭素社会を本気で造る国の根本政策が無いからです。これがない限り、今回もEU・途上国(米中)連合に押し切られるでしょう。
敢えて日本が主張すべきは京都議定書の「共通だが差異ある責任(Common but Differentiated Responsibility)」を全ての参加国に再確認させることでしょう。






 先日からケニアに出向していた中川鉄平さんが帰国致しました。
先日からケニアに出向していた中川鉄平さんが帰国致しました。 こんにちは☆国際業務部の西本若菜です。
こんにちは☆国際業務部の西本若菜です。